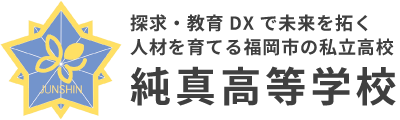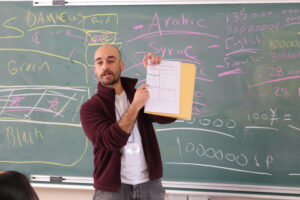SLOW FOOD LEARNING JOURNEY #5 -半年間の学びを語るインタビュー-

本校から4名の生徒が参加した全国規模のプロジェクト SLOW FOOD LEARNING JOURNEY。貴重な学びを言葉にすることで今後の成長につなげるためインタビューを実施しました。
SLOW FOOD LEARNING PROGRAMとは
一般社団法人 日本スローフード協会が主催。一般財団法人三菱みらい育成財団の2024年度助成事業に採択された教育プログラムで、全国の高校生が参加。2024年10月からスタートし、大学生メンターのサポートを受けながらオンライン研修、徳島での実地研修、イタリアスローフード協会本部とのオンラインプレゼンという半年間を過ごしました。
言葉で振り返り学びにつなげるインタビュー
今回は座談会形式のインタビュー、そして、単独でのインタビューの2つを実施しました。言語化することで自分の考えを整理し、未来の成長に活かすことが主な目的です。
同時に、私たち教員としては成長した姿を後輩にも示せるようにすることで、学校の未来へもつなげたいとも考え、研修が終了した今インタビューすることにしました。
座談会
2年探究クラスの太田先生に、座談会の3名にインタビューをしていただきました。

プログラムで最も記憶に残っていることは何でしょうか?
Kさん:徳島での研修でコエグロを作ったことですね。
Iさん:地元の農家でのフィールドワークが一番印象に残っています。実際の体験を通じて、生産者の方々の思いや苦労を直接感じることができましたし、食材1つ1つの大切さや、それにそれを支える人々への感謝の気持ちが深まりましたね。食卓に結構いろんな食べ物が並ぶ時に、この食べ物はどういう経緯で私たちの間に届いたのかなって考えることは多くなりました。
Rさん:やはり徳島合宿ですね。コエグロづくりなど、体験したことのないことをたくさんできたことが大きな印象に残っています。


プログラムの中でテーマを設定し最終発表するまでにフィールドワークや仮説検証をしたと思いますが、その中で難しかったこと、それからどう乗り越えたか聞いてみたいですね。
Rさん:仮説検証が難しかったです。ウェブ上の情報だけではなく、農家さんに直接インタビューをすることで解決しました。
Iさん:お祭りに関わる食材を活用したレシピを提案する際に、地元の人のニーズや思考を把握するのが難しかったですね。様々な仮説検証をすることで、各地域のお祭りにも目がいくようになり、その意味やどんな願いが込められているのか思いをはせるようになりました。
Iさん:規格外野菜について調べたんですが、ウェブ上には大量のデータがあって、どのデータが一番いいのかが分からなかったことが難しかったですね。

半年間で一番成長したことは何でしょうか?
Kさん:スライドづくりが格段にレベルアップしました。
Iさん:様々な人がいて異なった考えがあることがわかりましたね。相手の考えを想像したり尊重できるようになりました。
Rさん:大学生メンターさんとのやり取りの中で、プランニングをしたり課題設定をするスキルが大きく伸びたかなって感じました。

ありがとうございました。目の前で半年間見てきて大きく成長したことは私たち教員も実感しています。

(撮影者)本当にそうですね。特にイタリアとのオンライン最終発表の前日のリハーサルからの伸びはすごかったですね。スライドも発表も別物・別人のようでした。

その通りで、見学された先生方は皆感激されていましたね。それでは3名の皆さんインタビューありがとうございました。
地域を変える!純真高校生のスローフードへのさらなる挑戦に期待
SLOW FOOD LEARNING プログラムを通じて、思考力も実用的スキルも大きく成長した純真高校の4名の生徒たち。今後の活躍に期待です。