『トランスジェンダー生徒と学校』をめぐる読書会 -第4回職員研修(第2部)のレポート-

先日、本校では第4回職員研修の第2部として、書籍『トランスジェンダー生徒と学校』(土肥いつき著)をテキストとした読書会を行いました。
ファシリテーターは、哲学プラクティショナーであり、本校の探究コーディネーターでもある安本志帆さんです。著者の土肥さんにも引き続きご参加いただき、教職員同士の率直な対話とともに、深く考える読書の時間となりました。
「まず何から始めるか」をめぐる対話

読書会の冒頭は、参加者による自由な質疑応答から始まりました。
最初に挙がった質問は、「教員として、まず何から始めたらよいのか」というものでした。
これに対して示されたのは、レインボーのシールやタグを身につけるなど、教員としての姿勢を「視覚的に示す」という実践でした。生徒が「ここなら話してもいいかもしれない」と感じられるきっかけをつくることの大切さが、参加者の間で共有されました。
続いて、「アンケートの性別欄に『その他』を設けるべきか」という、実務に直結する質問も出されました。これに対しては、統計上の必要性がない限り、そもそも性別を問う必要があるのかを考えること、仮に設ける場合でも、「戸籍上の性別を指す」「自己認識上の性別を指す」など、何を問うているのかを明記する注釈が不可欠であるとの指摘がありました。
性別欄の一行は、単なる書類上の処理にとどまらず、学校がどこまで具体的な配慮を実行しようとしているのかを示すものでもあるという視点は、これまで十分に意識してこなかったものでした。
また、若手教員から出た「まずは、何から勉強すれば良いか」という質問に対しては、差別を個人の問題ではなく、社会の構造として捉え直す「社会モデル」という視点の重要性が語られました。この視点を持つことで、「なぜ社会は差別を必要としてしまうのか」という根源的な問いへと、思考が開かれていくことが示されました。
そのほかにも、近年生徒からのカミングアウトが増えている一方で、トイレや更衣室などの環境整備が追いついていないという現場の切実な声や、「自分自身も“レインボーの一員”なのだと感じた」「男女二元論に明確に当てはまる人の方が少ないのではないか」といった、参加者自身の認識の変化を示す意見などが交わされました。
学校の中で積み重なるジェンダー葛藤 幼少期から高校まで

自由討議を経て、いよいよ書籍の輪読へと移りました。取り上げたのは、第4章「学校の性別分化とトランスジェンダー生徒のジェンダー葛藤」です。
教員が交代で読み進めながら、幼稚園・保育園、小学校、中学校、高校と、当事者たちの語りを追体験していきました。
幼少期の場面では、ピアノの発表会で渡されたスカートに「それは嫌」と大泣きした話や、望まない化粧を施されて強い嫌悪感を抱いた話などが紹介されました。そこには、「男の子らしさ/女の子らしさ」や「性別のあり方」が、本人の意思とは無関係に当たり前のものとして押し付けられていく原体験が、はっきりと刻まれていました。
小学校に上がると、「男女別の性教育」「男女別の整列・行事」といった学校システムが、本格的に子どもたちを分け始めます。
中学校では、制服の着用によって男女の区別がより明確になり、生徒間の関係性にも変化が生まれていきます。
「制服の同じもの同士で分かれる空気が強くなり、小学校との違いにしんどさを感じた」という言葉に、多くの教員が深く頷いていました。
高校の場面では、「タイツではなく靴下を履きたい」といった「ささやかな要求」が、当事者にとってはいかに「切実な一歩」であるかが描かれます。一方で、男女別校舎の学校に通い、「男子校舎へ行きたい」という願いを、非現実的だと感じて言葉にできなかった生徒の語りも紹介されました。
「要求として言語化できるかどうか」が、支援につながるかどうかの分岐点になってしまう現実。その重さを、私たちは改めて突きつけられました。
当事者の語りから見えてくるもの
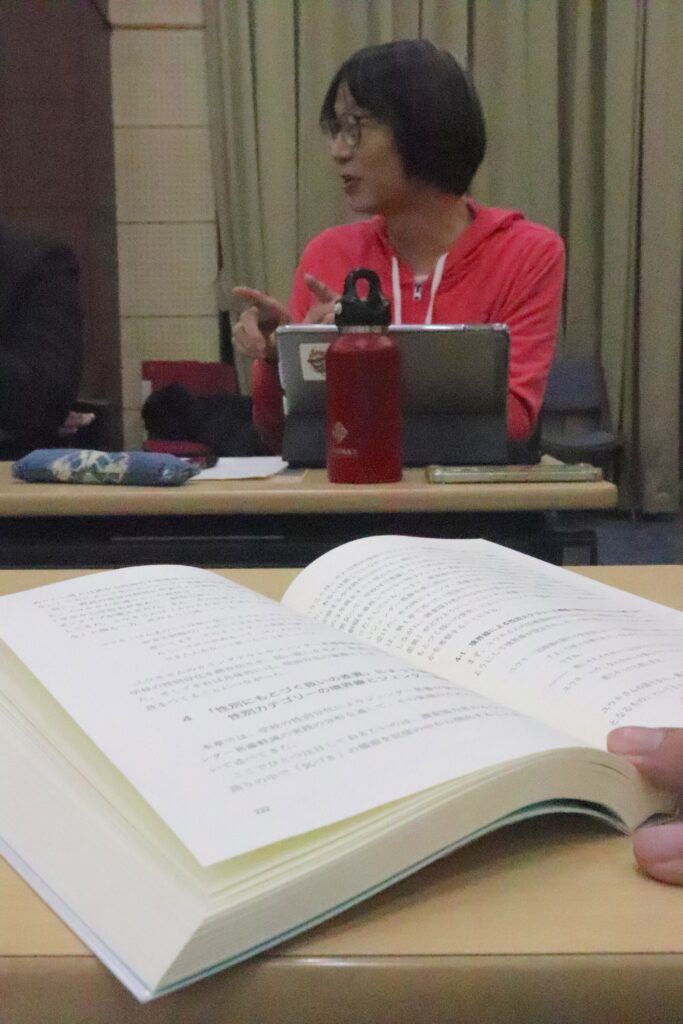
輪読後の感想共有では、参加者一人ひとりから、自分の考えや姿勢を見つめ直す言葉が語られました。
「研修を重ねて知識はあるつもりでいたが、『知ったつもり』になっていることこそが、一番差別的なのではないかと感じた」という声に象徴されるように、当事者の語りは参加者一人ひとりの認識を揺さぶり、「理解しているつもり」でいた自分自身を問い直す時間へと変わっていきました。
土肥さんが研修でも話されていた「行くも地獄、とどまるも地獄」という言葉の重みも、改めて実感として迫ってきました。
最後に土肥さんから示されたのは、「何度も読み返す中で、最後に残ったのは、『よくぞ生き抜いてきたな』というリスペクトでした」という言葉でした。
当事者を「支援する側」「支援される側」という関係で捉えるのではなく、同じ場で学び合う存在として見つめ直す――そんな感覚が、自然と共有された読書会でした。
「答えのない問い」とともに歩む学校でありたい
今回の読書会を通して、私自身が最も強く感じたのは、「難しいから」「わからないから」と言って、このテーマから距離を取ることだけはしてはいけないということです。
生命の危険にさらされながらも、必死に日々を生き抜いている子どもたちが、確かにいます。
学校は、その子たちにとっての「幸せ」を感じられる場になれているのか。
あるいは、知らず知らずのうちに、その子たちを追い詰める側に回ってしまってはいないか。
その問いから目を逸らすことなく、本校に関わる教職員全員で、これからも共に考え続けていきたいと思います。
本校は、「正解を持っている学校」ではなく、「答えのない問いを共に考え続ける学校」でありたいと考えています。
もしこの記事をお読みになった方の中で、「一緒に悩み、一緒に考えながら、これからの学校づくりに取り組んでみたい」と感じてくださる方がいらっしゃれば、本校は、そうした仲間との出会いを心から歓迎します。
投稿者プロフィール

- 純真高等学校校長
最新の投稿
 お知らせ2026年1月8日2026年最初の校長講話
お知らせ2026年1月8日2026年最初の校長講話 校長Blog2025年12月18日『トランスジェンダー生徒と学校』をめぐる読書会 -第4回職員研修(第2部)のレポート-
校長Blog2025年12月18日『トランスジェンダー生徒と学校』をめぐる読書会 -第4回職員研修(第2部)のレポート- 校長Blog2025年12月17日第4回職員研修ブログ:学校はこの問いにどう向き合うのか -「ジェンダー」をめぐる職員研修から考える-
校長Blog2025年12月17日第4回職員研修ブログ:学校はこの問いにどう向き合うのか -「ジェンダー」をめぐる職員研修から考える- お知らせ2025年8月7日本校の教育改革の取り組みが教育専門誌「キャリアガイダンス」に掲載されました
お知らせ2025年8月7日本校の教育改革の取り組みが教育専門誌「キャリアガイダンス」に掲載されました


